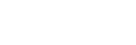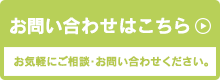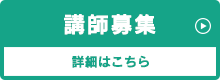受験生の皆さん、お疲れさまでした。
受験生を支えてこられた保護者の方々、お疲れさまでした。
「今年の問題はどうだったのか?」「周りはできているのか?」気になってしまうと思います。
しかし、力の限りを尽くした受験生諸君は、まずは頭を空にして、ゆっくり休んでください。
それでも、どうしても気になるという都立高校受験生のために、当塾の独断と偏見に満ちた問題分析を掲載させていただきます。
当記事は、受験生や受験生の保護者の方に読んでいただくために執筆しておりますが、講師陣の研鑽の場でもあります。これから当塾で高校受験をされる方々のために私たちは常に最新の入試問題を研究し、指導内容に反映させるべく精進しております。毎年、予想平均点ピタリ賞を狙いつつ、好き放題に論評しつつ、都立高校入試に対して研究を深めております。ここに掲載されていることは、当塾の独断と偏見の塊であることをご理解のうえ、お読みください。
ちなみに、昨年度の入試問題分析を答え合わせをしてみると・・・
当塾予想平均点-実際の平均点
英語+1.1点
数学+0.3点
国語+1.1点
理科+0.2点
社会+0.5点
【概要】
昨年度は都立高校入試の平均点が公表されるようになったH15年度以降で最高の平均点を記録する、非常に易しい入試問題であった。今年度はそこからは難化し、5教科で310点程度の平均点を予想する。昨年度から5教科で15~20点のダウンということで、昨年度と比較すれば、ボーダー得点が下がっている高校が多いものと推察される。最も影響が大きかったのは理科だ。完答式の問題が増加したこと、問題文の読み取り能力が問われる問題が多かったことで、平均点が10点近く下がっているはずだ。
5教科トータルで見れば、今年度の入試問題が特別に難しかったわけではない。昨年度が簡単すぎただけで、例年と比較すれば「標準~やや易」の水準だ。特に、英語・数学・国語の3科はいずれも易しい部類と言える。
【予想平均点】
英語 65点(昨年度66.9点)
数学 63点(昨年度61.7点)
国語 72点(昨年度75.9点)
理科 55点(昨年度66.8点)
社会 53点(昨年度55.5点)
【教科別分析・コメント】
英語 やや難化(昨年度比) 予想平均点65点
今年度は昨年度(平均点66.9点)からはやや難化し、平均点は65点を予想する。
出題形式は例年通りで、設問の難易度は標準レベルだったが、平均点の押し下げ要因として大問2の語数の増加を考慮した。しかし、今年度の問題は、昨年同様全体的には解きやすかったので、中~上位層には得点しやすい問題だったと言える。当塾塾生の自己採点平均は、86.3点だった。なお、指導要領改訂の影響で語彙レベルの難化が想定されるが、昨年度と比べて、難化している印象はなかった。これまでであれば注がついていた単語に注がつかなくなってきてはいるが、英検3級レベルの英単語と熟語を習得していれば十分対応できるレベルである。しかし、新指導要領では、中学卒業時点で2000語を超える語彙力を求めている(旧課程では1200語だった)ため、来年度以降さらに高いレベルの英単語が出題される可能性は十分あるだろう。
以下、大問別に分析する。
大問1:標準
当塾塾生の正答率とリスニングテストの台本に基づき、難易度は標準レベルと推定する。
問題B Question2は、差がつきやすいリスニングの記述問題だが、今年度の問題は比較的簡単だった。質問の英文が長いので一見難しく感じるかもしれないが、情報が多くなればそれが回答を絞り込む手がかりにもなる。1回目で正確に質問を聞き取り、2回目の放送で確実に正解を書けるようにしたい。リスニングの記述問題では、放送された文を正確に書き取ることが重要なため、対策として、「ディクテーション」という訓練が有効だ。「ディクテーション」とは、英文を聞いて一時停止しながら文を書き取る訓練のことだが、当塾では模試や過去問演習の復習課題として毎回取り組ませている。今回の問題でも該当箇所の英文を的確に書き取れれば完答できたが、主語の選択や人称代名詞のミスには注意したい。
大問2:やや難
大問2の図表の読み取りは、都立入試の英語の中で最も読解力を要する問題だと考える。今年度は昨年度に比べて、大問2の単語数が増加していたため、いつもより時間がかかった受験生もいたかもしれない。英語を苦手とする塾生には、大問2の1と2を後回しにして、大問3と4を先に取り組ませることもある。その理由は、大問3と4に時間をかけた方が得点につながりやすいからだ。文中には特に難易度の高い単語や文法はなかったが、新指導要領で新たに加わった「仮定法過去」が使われている文章があった。
大問2が難しい要因の一つは、文中に直接的な根拠を見つけにくいことにある。
例えば、今年度の大問2の1は、(B)の選択肢を選ぶ際に、you(Lucy) can use the line that you usually useという文に着目する必要があった。Lucyが普段使っているLineは、South Lineだから、それを手掛かりにしてAjisai Stationを選ぶのだが、このような段階を踏んで、英文で内容を読み取るのは簡単ではない。また、大問2の2(A)では、時間の計算が求められるし、(B)では、I have played one in a music class beforeやI want to do it againというセリフから選択肢を推測する必要がある。会話文中には正解となる単語(wadaiko)が出現しないため、間接的に回答を絞り込まなければならない。このような理由で、大問2は、大問3や4と比べて難易度が高いと考えている。
今年度の英作文は、「もっと練習したいこと(something that you want to practice more)」についてだった。比較的書きやすいテーマだったと思うが、一から考えて英文を書くと思いのほか時間がかかる。英作文対策は、過去問や模試で出題された内容を繰り返し解き、事前に用意した英作文をすぐに書ける状態にしておくとよい。今回と似たテーマとして、平成20年度の「将来取り組んでみたいこと」があった。ちなみに当塾塾生は、過去問15年分ほどの英作文テーマを受験前に準備し、それらを1分で正確に書けるよう修行を積んでいた。このため、多くの塾生は1分で12点(満点)を手中に収めたはずである(当塾では入試直後の再現答案を添削している)。過去問と同じテーマが出題される可能性は低いが、過去問のテーマで準備した英作文がそのまま使えることもあるから、事前に用意しておくとよいだろう。
大問3:標準
出題形式は昨年度と同じで、標準レベルだった。単語数は昨年度に比べてやや少なかった。大問3の問6に関しては、今年度は昨年度と同じだったが、出題形式が変わることがあるので注意したい。例えば、2024年度は、空欄に入る適切な単語を選ぶ問題、2023年度は、空欄に入る適切な文章を選ぶ問題、2022年度は、大問4の問2のような本文の内容に沿って文を並べ替える問題が出題されたことがある。この問題は、英文を読む前に知っておいた方が解きやすいため(あとでその問題に気づくともう一度読む必要があり手間が増える)、大問3を解く前には、設問(特に問6)を確認しておいた方がよいだろう。例年通り、いずれの問題も指示語に注意して下線部の前後を丁寧に読めば、解答の根拠を見つけることができるが、問4がやや難しかった。下線部の直前に選択肢ウとよく似た英文があったため、それを選んだ受験生が多かったことが推測される。
大問4:標準
出題形式は例年通りで、難易度は標準レベルだった。単語数は昨年度に比べてやや多かった。特に問3の(3)の正答率が低いと思われる。文中に2つの文で説明されていることが選択肢では1文で表現されているため、それを同じ意味として捉えられなかった受験生が多いことが推測される。この問題だけに限らないが、正解の選択肢を選ぶために、関係代名詞や受身などの正確な文法知識も求められている。また、仮定法過去(I wish I could〜)やso〜that構文が使われている文章もあり、文法レベルは例年と比べて高くなっている印象を持った。
最後に、単語レベルについての個人的な感想を一言付け加えておきたい。講師目線では、今年度も特に難しい単語は使用されていないと判断しているが、一昔前には、今回の英文にも登場するposterという単語にも注がついていた時代(2022年度)もあった。「こんな簡単な単語にも注がつくのか」と驚いたものである。しかし、最近の英文の注は減ってきており、当然のことながらposterにも注はつかない。また、今年度の英文にも出てくるthanks toやbe proud ofという熟語も一昔前には注がついたが、今年度は注がついていない。このことから都立入試の英単語レベルが以前と比べて上がっていることは確かだ。しかし今後はさらに単語レベルが上がる可能性もあるだろう。新指導要領の影響で教科書の単語も格段に難しくなり、最近は「こんなに難しい単語が中学生の教科書に出てくるのか」と驚くこともある。このため、都立入試の単語レベルは、今後さらに上がるのではないかと身構えている。どのくらいレベルが上がるのかは分からないが、いつレベルが急上昇しても対応できるように、当塾では、英検(準2級・2級)の早期取得を目標として、英単語学習にも力を入れている。単語を覚えすぎて損をすることはない。早期に単語力を高めておけば、その知識が高校入試のみならず、高校入学後の英語の授業、さらには大学入試でも大きな武器になると考えている。
数学 やや易化 予想平均点63点
毎年のことであるが今年度の数学も例年通りの難易度と言える問題が多く、過去問の演習を繰り返していた受験生にとってはよく知った形式の、見たことあるような問題ばかりが並んでいた。
大問3・4・5の最後の設問は難しい問題が出題されがちだが、昨年と同様に今年度の問題も全て『捨て問』と言えるほどの難しさはなく、上位校志望者であればどれもトライする価値のある問題であった。正答率が3%以下になるような出題は昨年に引き続き今年も出題されなかった。この出題が続くようであれば数学が得意で数学を得点源として考えている受験生や上位校の受験生は『捨て問』と考えずに全ての問題にチャレンジしていく必要がある。
平均点は昨年とほぼ変わらず63点と予想する。
以下、大問別に分析する。
大問1:標準
問2の文字式の計算で符号のミスをした受験生が多かったと思われる。単純な文字を使った計算問題で難易度も決して高くないが、式の後半部分を分数の式のように一括りにして計算してしまうミスが頻発したと想定される。実はこの問2では5年連続で式の後半が分数の多項式で符号が-のものが出題されていた。過去問の解き方に慣れすぎてしまいミスが出た受験生も少なくなかったと思われる。
問7では二乗に比例する関数の変域についての出題があった。大問3で頻出の問題であるが今年度は大問3が一次関数の問題だったことからここでの出題となった。これは大問3が一次関数だった2021年度入試でも全く同じ出題がされていた。
そのため例年であれば問8で出題される平面図形の角度の問題は出題がなかった。
問8は「1〜5の数字が書かれた5枚のカードの中から同時に3枚のカードを取り出したときに書いてある数の和が10以上になる確率を求める問題」であった。取り出すカードが3枚である点が珍しいと言えるが、全部で10通りの取り出し方しかないため易しい。
大問2:やや易
図形や数列など様々な問題について「先生が示した問題」について答えを選び「Sさんのグループが作った問題」について証明する問題。今年度も例年通りの出題内容と言える。昨年以上に「先生の示した問題」も「Sさんのグループが作った問題」も内容が分かり易く、証明も式に当てはめて計算したら完成する書きやすい内容だった。過去問の繰り返しで似ている証明問題を書くことに慣れている受験生であれば満点の証明も容易に書ける内容だ。
大問3:やや易
例年通りの出題内容。全く同じ問題を解いたことがあるのではないかと錯覚してしまうほどの典型問題であった。難問が出題されることも度々ある問3も定石通りに点Pのx座標を文字で置き、面積を表せば求められる問題で難易度は高くない。過去問や模試の段階から諦めて捨てることなくチャレンジを繰り返していた受験生であれば「取れる問題」だった。
大問4:標準
問1は例年同様角度を文字で表す式を選ぶ問題で難易度も例年並み。
問2①の証明問題は円周角について正しく理解し、証明に反映することができればシンプルに短い文で満点が取れる易しい出題であった。仮定で判明していることを書くだけでも部分点には貰える問題なので空欄の白紙回答だけは絶対に避けなければいけない。
問2②の問題が今年度の数学の中では最難だった。四角形AORQが台形であることと三角形ASQと三角形RSTが合同であることを見つけられれば簡単に解ける問題だが、そこに至るまでに多くの情報を整理したり相似を見つけたりしなければならないので難易度は高めだ。数学で高得点を求めている生徒以外は時間をかけずに飛ばすべき問題だった。
大問5:標準
問1では珍しく体積を求める問題だったが、条件を正しく図に書き込み空間図形が正しく見えていれば容易に解ける問題だった。
問2は空間図形を正しく切り取り平面図形に直して三角形PHFの高さを三平方の定理を使って求めれば簡単に答えが求められる。
空間図形に慣れていない受験生には難しい問題に見えるが、捨てるほど難しい問題ではなかった。
国語 難化 72点
問題形式的にはほぼ例年どおりで全く変化が見られなかった。
全体的に解きやすい設問が多く、今年度も平均点が70点を上回り、5教科中最も高くなる見通しだ。当塾塾生の自己採点結果でも上位層は90点を超えている状況が確認できている。ただし、非常に易しい設問が多かったここ2年と比較すれば、正答率75%以上の設問数が若干減少していると思われる。入試問題として辛うじて適正な難易度となっていると感じた。
以下、大問ごとに分析する。
大問1・2
例年どおり、易しい漢字の問題が10問並び、失点が許されない。当塾塾生の自己採点では、1名のみ1問ミスしていたが、それ以外の人は全問正解であった。
今年度は驚くほど過去に出題歴のある漢字の出題が多かった。昨年度も2問が比較的近年に出題された問題であったことを記したが、今年度はなんと5問が最近に出題されたことのある漢字であった(「跳躍」(H29)、「喝采」(H31)、「郷里」(H30)、「縮める」(H25)、「旅券」(H28、H22))。これだけ過去問題と重複するのであれば、漢字については過去問題を15年分程度遡って学習しておいてもいいかもしれない。
大問3
全体的には最も易しい大問であったと分析している。ただし、問1と問3が正答率で7割を下回っていると予想する。正解を選ぶにあたっては、行間を適切に読み取ることも求められており、しっかりと差がつく問題になっている(塾生は7割の生徒が全問正解であったので、易しかったことは確かだろう)。
大問4
奇問・難問はなく、いい出題だと感じた。特筆すべきは問4である。これは直接的な記述を探し出して終わる問題ではなく、「論理的思考」を問う設問になっている。国語の問題としては、新しい傾向といえるが、近年では大学入試における共通テストや都立高校入試の英語大問2で同様の能力が問われるようになってきている。作問者にもおそらく挑戦的な出題意図があっただろう。意欲作の問題(選択肢のつくりも含めて)であると評価したい。そして、問4が大問4の中で最も正答率が低くなっているはずである。塾生たちの自己採点でも正答率が6割程度で、国語全体を通してみても最も低かった。
大問5
歴史的仮名遣いの設問がなくなったため、「秒で解ける」簡単な問題は減った。近年定着している文法の識別問題は「ない」(助動詞/形容詞)であり、昨年度と比較すれば確実に難化している。とはいえ、「ぬ」に言い換えができるかどうかで、小学生でも解くレベルの文法問題であり、対策をしている受験生にとっては全く問題ない。当塾でも直前期に同様の識別問題は対策をしていたため、間違ってしまったのは1名だけであった。その他は、読解力問われる出題がしっかりされており、適度に差がつく良問が並んでいる印象だ。
理科 難化 予想平均点55点
大問の構成や配点は例年と変わらず、大問1・2がいわゆる小問集合、大問3以降は順に地学、生物、化学、物理と続いている。例年と比べて圧倒的に情報量・文章量が増加(フォントサイズこそ変わっていないものの行間と文字間の幅が縮小)し、多くの受験生を戸惑わせたと思われる。完答式の問題は昨年が1問のみだったのに対して今年度は8問と大幅に増加し平均点を押し下げる要因になっている。文量が増えた影響で時間不足に陥った受験生や情報が処理しきれずに苦戦を強いられた受験生も少なくなかったと思われる。難問と言えるほど難しい問題は無かったが、正答率が80%を超えるような「誰でも解ける問題」もほとんどなく平均点は昨年度よりも大幅に下がって55点と予想する。また必要や知識を入れてさえいれば時間をかけずに正答を選べる問題が大幅に減り、どの問題も知識だけでは解くことは難しく、問題文を読み込み理解する力と情報を正しく整理し処理する能力を求める問題が多かった。
大問1:標準
例年通りの小問集合が6問。すべての問題が基本的な問題で難易度も高くないが、例年と比較して文章が無駄に長く、読むのにも時間がかかるようになった。問4は質量と体積から密度を計算し、その物体が鉄なのか銅なのかを判別する問題なのだが、鉄と銅の密度が僅差であるため、107.52÷12.0もしくは118.05÷15.0の計算をする必要があり、時間がかかる問題だ。一方で、問5は質量と底面積から圧力を求める問題であるが、こちらは圧力が最大であるものを選択する問題なので、計算することなく正答をえらぶことができる。問6は遺伝についての簡単な知識問題であるが、例年の小問集合と比べると情報が多いため、きちんと問題を読み整理して解く能力が問われている。解くうえで必要な知識としては多くはないものの、どの問題も文量と情報量が増え、読解力と時間が必要な出題となった。
都立高校入試では最後にこの理科のテストが実施されることを考えると、今年度の問題は例年以上に受験生に大きな負担感と疲労感を与えたことだろう。
大問2:やや難
例年通りレポートをヒントに解く小問集合4題。この大問も大問1同様に情報が増え、解くのに時間がかかるものが増えた。問3と問4はともに問題文やレポート文の読み取りが難しく正答率は低くなると思われる。
大問3:標準
地層に関する一般的な出題内容。問1・問2は単純な知識を問う設問で確実に正解をしたい問題だ。問3も典型問題であるが、解くうえで重要な標高については図に記されておらず、結果が書かれた文章から読み取らないと解けない問題であった。問4は問題文が読み取りにくいが、どこの地層の話をしているのかを正しく読み取ることさえできれば知識はなくても解ける問題であった。問3・問4は近年の傾向ではあるが、知識よりも読み取りの能力が問われる出題であった。
大問4:やや易
細胞分裂に関する出題。この大問も問われている知識は簡単なものであるが、問題文を正しく読み取る能力が求められる設問が多かった。正しく読み取ることができれば問われている内容は非常に容易なものであるが、長い文章問題を読み取ることに慣れていないと時間もかかる上に誤答をしかねない。
大問5:やや難
実験の内容は超頻出の炭酸水素ナトリウムの熱分解についてだが、設問がどれも少し難しく計算問題も簡単ではなく時間のかかる大問だった。
大問6:やや難
こちらも頻出の電流と磁界に関する出題。問1の計算問題は電力量を求める公式を覚えていれば難なく解ける。問2・問3は電磁石とモーターの仕組みが分かっていないと難しい問題だったが、2018年度の2021年度の入試問題で同単元の出題があったときと設問が酷似しているので、過去問の演習量が重要であることは間違いない。
社会 難化 予想平均点53点
知識だけではなく、問題文を読み解いて正解を導く能力が例年以上に問われる設問が多かったことから、平均点は若干低下していると予想する。知識を問う問題も一部に難化が認められる。しかしながら、当塾塾生の自己採点結果の平均は昨年度を若干上回る81.6点であったことからも(当塾塾生の学力水準・受験校は昨年度とほぼ同水準)、「絶対に取れないな」という問題は存在せず、上位校受験者は高得点が要求される入試問題になっていると言える。なお、論述問題は昨年度に引き続き3題で、今後は増加することはあっても再び2題に減少することはないと見ている。今年度の3題は、いずれも書きやすく、埋めたにもかかわらず部分点さえ出ない答案はほぼないはずだ。ただし、論述問題に必要以上に時間をかけてしまう受験生が一定数存在する。前述のとおり、社会には問題文や図表を読み解く必要のある問題も多いことから、試験時間をもう少し長く欲しいという人もいたかもしれない。そのような事態に陥りそうな人は、予め論述問題の答案作成をしっかりと練習しておくことが肝要だ。
以下大問ごとに分析する。
大問1
いつもどおりの小問集合。昨年度と比較すると問3の正答率が少し低下するかもしれない。昨年度は国会の種類「特別会/臨時会」の区別、今年度は「国庫支出金/地方交付税交付金」の区別が問われている。いずれも、いいところを突いていると思う。マーク式でも正確な語句知識を問うのだという明確な出題意図を感じる。受験生が混同しそうな用語を狙っているのだ。昨年度、ここで若干名失点させてしまったため、今年度は公民用語を最後まで徹底させることを課した。結果として、塾内は全員正解できていたので、非常にほっとした。
大問2
この大問は読解力・推論力も問われるため、難しくなる年が多い。今年度は、まさにそのような年に当たっている。大問全体の正答率が5割を若干下回っていると思われる。
大問3
大問2ほどではないものの、読解力・推論力を要する設問になっている。上位層は失点することはないだろうが、中位層で差がついているように思う。誰でも正解できる易しすぎる問題という感じではない。
大問4
例年、最も差がつくのが歴史の大問であり、今年度も例年どおり差がつく問題になっている。実は、論述問題を除く3問全てで当塾塾生は全員が全問正解であった。当塾での取り組みは、昨年度の記事にも記載しているのでここでは詳細は割愛する。問2はやや難しい。文化史であるうえに、元禄と化政の江戸時代の中での区別まで必要だからだ。しかしながら、「元禄/化政」を区別しないと解けない問題は過去にも出題があり、過去問演習時に塾内では徹底することができた。問4はここ7年程度の間に複数回出題されているものが多く、過去問題の演習精度が問われる。なお、当塾では過去問題演習を通して「国家総動員法」「大阪万博」は年代の暗記を徹底できており、当然のように全員が正解していた。都立高校受験においては、歴史は地理以上に努力がそのまま点数に直結する。ここで周りに差をつけるだけの勉強をしておかなくてはいけない。
大問5
論述を除く3問とも全問正解したい問題であるし、できる問題である。問1はド定番の憲法条文の人権分類問題である。今年度は「社会権」を選ぶということで、昨年度の「平等権」から難化している。ただし、くどいようだがこれはド定番の問題である。失点した受験生が一人でもいたとすれば、その受験生を担当した社会の講師は猛省するべきだろう。問3は財政政策と金融政策の中身を問う問題で苦手な受験生が多い箇所である。この大問ついては、昨年度よりも若干の難化であると分析する。ただし、上位校・中堅上位校の受験生は全問正解しておくべき水準である。
大問6
読解力・推論力・グラフ読み取りが必要であるが、逆に言えば問1などは知識的にはほとんど不要で楽勝な問題であった。問2・3は取りこぼす受験生が一定数いたと思われる。
難易度は昨年度と似たようなものだと思うが、知識勝負の問題がやや減少している。そして、問題文と図表の読み取りや推論力がより求められている。これは一般的な社会のテキストで鍛えきれない部分であるが、毎年同様の問題はたくさん出題されている。都立高校入試の過去問題や「都立そっくり」を打ち出している模擬試験で演習を積み、解くためのコツを掴むまで復習を徹底することが必要不可欠だ。